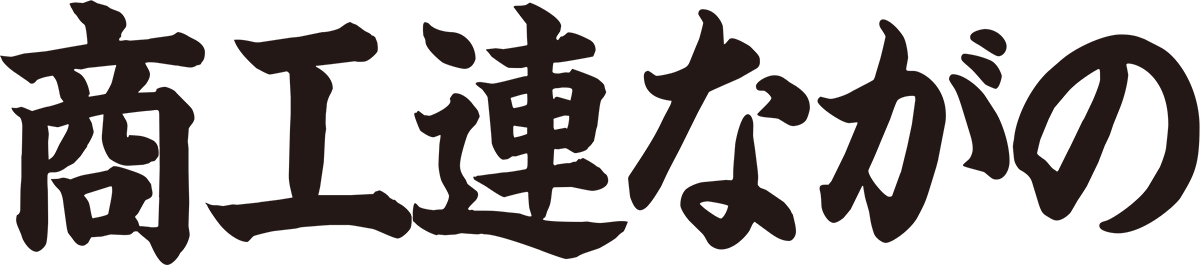ONE POINT ADVICE
法律ワンポイントアドバイス職種限定合意と
配転命令権について

弁護士
諏訪 雅顕 氏
1 労働者が職種を限定して入社してきた場合、会社として自由に配転させても良いのか、配転命令に限界があるのか、職種限定合意というものがどこまで尊重されるのか、これは古くから問題とされてきた伝統的な論点です。
2 この論点に関し、昨年4月最高裁の判決が出されました。
原告Xは、県の社会福祉協議会と労働契約を締結し、同法人が経営する福祉用具センターで福祉用具の改造・製作等に携わる主任技師(溶接ができる唯一の技術者)として約18年間働いていましたが、突然同センターはXに対し、総務課(施設管理担当)への配転を命じました。Xはこの配転命令が違法であるとして争ったところ、最高裁は、労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する合意(本件では、書面等はなく黙示の合意であった)がある場合は,使用者は労働者に対し、労働者の同意を得ることなく配転を命ずる権限を有していない旨判示し、同配転命令を違法と判断しました(最判令和6年4月26日滋賀県社会福祉協議会事件)。
3 本件事件の一審は、本件において黙示の職種限定合意があったと認めた上で、同センターは本件配転命令の頃には福祉用具の改造等をやめようと決めていたこと、実際に既存の福祉用具を改造する需要が激減しており月収約35万円のXを専属として同センターに配置する経営上の合理性はないと考えられたこと、本件配転命令当時総務担当者が病気により急遽退職し欠員状態となっており同担当者を補填する必要があったこと等から、本件配転命令は権利濫用とはいえない、といった判断をしていました。
実は、従前の判例は、会社側の配転(転勤)命令の裁量(配転命令権)を認め、但し、同配転命令につき業務上の必要性が存しない時、業務上の必要性が存する場合であっても当該配転命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものである時、労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものである時等特段の事情がある場合には、同配転命令は権利の濫用となり許されないと解釈していました(最判昭和61年7月14日東亜ペイント事件等参照)。その後の下級審判決も概ねこれに従った判断をしてきていました。
これに対し、本件最高裁判決は、職種限定合意がある以上、使用者は配置転換を命ずる権限をそもそも有していないとしたものであって、使用者側の事情や必要性があっても職種を限定合意した労働者の意思を原則として無視してはならないと判断したものであり、特筆すべきであると思われます。
4 本件最高裁判決の根底には、労働に対する理念といったものがあるように思われます。人にとって労働とは、単に賃金を受け取るだけのものではなく、その人の人格を形成し人生を充実させる上で重要な意味を持っているものです。この判決は、労働者の意思を尊重することはその人の人格や尊厳を遵守することに繋がるものだということを訴えているように私には思われます。
近年、労働内容の多様化に伴い、就業する者のスキルを生かすべく職務や勤務地を限定した「ジョブ型雇用」を採用する企業が増えていますが、今回の判決は、こういった雇用形態はどうあるべきなのか示唆を与えていると思います。
他方で、配転がある程度自由にできないならば、その職種がなくなった時には自由に解雇してもよいのではないかという意見もあるようです。しかし、実務が積み重ねてきた整理解雇の4要件を覆してまで解雇権が認められる訳ではありません。あくまでも会社側でその事情(就業場所がなくなることやその必要性)を十分に説明し、類似する別の業務を紹介したり、有利な条件を提示するなどして、労働者の理解を得ていくことが求められていると考えるべきでしょう。